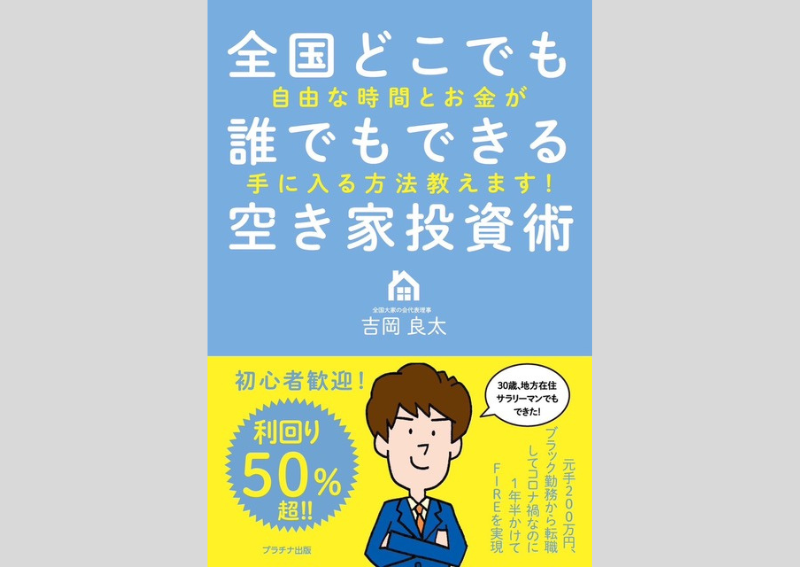賃貸オーナーとして反社会的勢力にどう向き合うか?

2018/07/17

■反社の現状と、どのように防ぐか
2018年1月、警察庁は暴力団の資金源対策の1つとして、銀行が新規の個人向け融資を行う際、警察庁の暴力団情報データベースにオンラインで照会できるシステムの運用を開始。暴力団排除の動きがますます強まっている。暴力団、いわゆる反社会的勢力(反社)排除の動きは1991年の暴力団対策法(暴対法)の制定以後、法律改正によって強化されてきた。この結果、年々暴力団の構成員が減少。警察庁組織犯罪対策部がまとめた「平成28(2016)年における組織犯罪の情勢」を見ると、2010年から順次始まった都道府県の「暴力団排除条例(暴排条例)」の施行を契機に急激にその数を減らし、16年には暴力団の構成員の数がはじめて2万人を切り、準構成員を含めた暴力団関係者の数が4万人を割り込み、その影響が少なくなっているようにも見えている。
しかし、「統計上は減ってはいても、実際の反社勢力が大きく減っているという認識はない」と話すのは、反社勢力の排除支援に強みを持つ企業危機管理の専門会社「エス・ピー・ネットワーク」取締役主席研究員で、反社対策を担当する芳賀恒人さんだ。そのうえで芳賀さんは現状を次のように分析している。
「現状は暴力団が表に出ないだけで、その意を受けた勢力が代わりに活動しているというようなイメージです。ですから、賃貸物件の契約で暴力団が出てきて取引することはほぼなく、その意を受けた人のさらにその意を受けた人というように潜在化しています。そのため入居時の反社チェックに取り組んでいても、表面的なチェックだけではそれを見抜くのは難しくなってきているというのがいまの状況です」
こうした背景から契約時には反社とはわからず、入居させてしまうこともあるという。
「契約段階ではわからないため、入り口でのトラブルというのは、むしろ減ったようです。ところがフタを開けてみると、住んでいる人が別人で、それが反社だったというような事案は増えています」(芳賀さん)
とはいえ、反社チェックをきちんとしておけば、こうしたことは賃貸契約そのものが違反で無効になるため、それを武器に退去を迫れば、比較的大きなトラブルにはならず、反社側も退去に応じているという。そのためにも契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入することが重要だと芳賀さんはいう。
「反社というと心理的に怖いイメージがありますが、弁護士、警察と連携をすれば何もできないほど恐ろしいものでもありません。きちんと対応すれば解決できる問題です」(芳賀さん)
一方、入居者が反社と見極めるにはどうするか。そして、どのように対処すればよいのだろうか。
「反社が入居しているかがわかるきっかけは、大体の場合は隣の部屋や近所の住民からの通報です。近所の人が管理会社や家主に『怖い人がいる』と相談や通報をして、調べてみたら反社だったというケースが多い。また、管理会社や家主が何もしないでいると、連絡してきた人の多くは何もしてくれないと警察に通報。警察が調べたら暴力団員だということがわかり、管理会社や家主に対策を求めてくるということもあります」(芳賀さん)
警察がその場で対応してくれればとも思うが、賃貸契約はあくまでも民間同士の契約なため、反社といえどもいきなり警察が来て追い出してくれるというわけではない。
「実務については、最初は弁護士さんへの依頼からになります。早い段階で手慣れた弁護士さんに依頼すれば、反社かの確認や警察への連絡、退去のための文書の通知や、実際の退去の際の手続き的なものも対応してもらえます。最近はトラブルが少なくなったとはいえ、オーナーさん1人でやるのは危険なので、やはり弁護士さん、警察との連携は必要です」(芳賀さん)
■暴力団より危ない半グレの実態
暴対法や暴排条例によって暴力団員の排除が進む一方、危険な存在になっているのが「半グレ」といわれるグループだ。半グレとは暴力団に所属せずに詐欺や恐喝、集団暴行などの犯罪を繰り返すグループのことで、元暴走族のメンバーが中心になっている。その資金源は“オレオレ詐欺”といわれる特殊詐欺、ヤミ金融、出会い系サイトの運営などで、その特徴はITやネット、スマホなどを巧みに操る。
「やってることは暴力団と同じですが、半グレは暴対法の対象にならないので、警察としては暴力団のような対応ができません。半グレの主力は30代~40代と若く、年齢の割に羽振りがよくキャバクラなどに頻繁に出入りしています。そうして関係を持った店からみかじめ料を集めるようになり、暴力団とトラブルになるというケースも出てきています」(芳賀さん)
当然ながら、この半グレが賃貸住宅に入り込むことはある。半グレが部屋を使っていることがわかるきっかけも、近隣住民からの通報によるものが多いという。
「オレオレ詐欺は電話を使うので、その電話をしている声が1日中聞こえて、気持ち悪いというような苦情が寄せられるケースが端緒になるといわれています。そうした情報を元に警察も内定捜査をして検挙しようとします。しかし、昨年まではアジトや拠点を2、3ヵ月使っていましたが、最近では10日ぐらいで変えてしまうため、情報を元に警察が踏み込んでも、すでにもぬけの殻で取り逃しているようなことが起こっているという話です。そのため警察も捜査のスピードアップが求められおり、さらに対応が難しくなっています」(芳賀さん)
こうした半グレや反社が好んで使う物件の特徴について、芳賀さんは次のように指摘する。
「複数のいろいろな人間が出入りしたり、5~6人が常駐しているということから、間取りはワンルームのような単身世帯用ではなく、2LDK、3LDKといったファミリー向けの広めのもの。また、特殊詐欺グループは角部屋という傾向があります」
次ページ ▶︎ | ■増える大麻プラント、見逃さないポイント
■増える大麻プラント、見逃さないポイント

こうした反社や半グレが、活動の拠点やアジトとして賃貸物件を利用するのとは別に、最近、大きな問題になっているのが、室内での大麻栽培だ。今年1月にも東京都文京区のマンションで火災報知器が作動し、住民からの110番通報をきっかけに大麻草の栽培が発覚、40代の男が逮捕された。また、2月には奈良県橿原市で、近隣住民から「大麻草の臭いがする」という110番通報から、家宅捜索が行われ、大麻草の栽培プラントを発見。30代の会社員の男2人が逮捕されている。
こうした大麻栽培が明らかになるなかで、大麻栽培が行われた家や部屋では、共通点があることがわかってきている。
その1つ目は、大麻には独特の臭気があり、玄関の隙間や換気口からその臭いが漏れることがある。具体的には大麻草そのものは「青くさい臭い」、一方、乾燥させた大麻は「甘い臭い」になる。
2つ目は、常に窓が雨戸や遮光カーテンで閉ざされている。大麻栽培では光量を調節する必要がある。そのため外から光が入らないように室内は暗闇にしておかなくてはならない。そこで光が入り込まないようにするのと同時に、臭いが外に漏れないように窓などに目張りがされている。
3つ目は、人が生活している気配がないのに、電気の消費が多く、電気メーターが早く回転している。大麻栽培は一定温度を維持しなくてはならない。そのため常にエアコンを稼働させる必要がある。加えて、水耕栽培しているケースもあり、こうしたプラントでは大量の水を循環させるため電気を使う。さらにこうしたプラントではときとして機械の故障などが起こり水漏れが発生することがある。
4つ目は、深夜になると頻繁に人の出入りがある。栽培に必要な土や肥料、機械などの持ち込み、収穫した大麻の持ち出しを夜中に行っているため、夜中の出入りが多くなるというわけだ。
■入居を防ぎ、退去させるために

反社、半グレ、大麻栽培といった問題を生じさせないためには、こうした人たちを見抜き契約しないことが第一。では、不審者をどう見極めるか。芳賀さんは「不自然なところを見つけることがポイント」という。
「たとえば、すごい高級車に乗っているのに女性を連れてワンルーム、1LDKの部屋を借りに来る。また、自分が住むといっていながら、電話で指示を受けて部屋を探したり、申込書や契約書を書いている人。こうした際には一言『ご自分で住まわれるんですよね?』と質問してみて、その反応を見るのも1つの方法です」
とはいえ、どんなに入居させないようにしても、完全にシャットアウトするのはなかなか難しい。そこで入居してしまった場合への備えも必要だ。その最大の武器になるのが居住者から常日の情報収集だと、芳賀さんはこう話す。
「早い段階で変だという情報があれば、早めの対応ができます。そのために居住者からの情報を受け付ける体制をつくっておきます。といっても、『不審な人がいたら連絡をください』というような直接的な言い方はしづらい。そこで、たとえばスーパーマーケットにあるようなご意見アンケートBOXの設置やメールアドレスを公開しておきます。このように要望や意見を集めるような態勢をつくっておけば、そういった情報も自然と集まるようになるのです」
さらに管理会社と契約している場合は、その連携も重要だ。
「新しく入居した人がどういう人なのか、個人情報は別にしても、不審な点はないか、きちんと確認する。また、入居1ヵ月後ぐらいにその人たちが住んでいるかどうか、様子を確認してもらうという方法もあります。管理会社も関係する問題ですから嫌とはいわないはずです」(芳賀さん)
家や部屋は究極のプライベート空間。だからこそ、犯罪の温床になるというわけだ。芳賀さんはこう話す。
「使い方次第では住居は犯罪のインフラや組織が活動するための拠点になる可能性があるという意識を賃貸住宅のオーナーさんには持っていただきたいと思いますね。そのためには契約書の作成や身分証明書の確認などのひとつひとつの手続きをおざなりにせず、会った瞬間から、手続きの最中まで不審なところはないか、なぜこの人はその物件を借りようとしているのかを考えながら見ていると、不審なところが見えてきます」
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。